多肉植物コレクションの記録が私の栽培レベルを劇的に向上させた理由
多肉植物を育て始めて5年、200種類のコレクションを管理する現在の私ですが、実は最初の2年間はかなりの失敗続きでした。エケベリアを徒長させ、ハオルチアを根腐れさせ、同じ失敗を何度も繰り返していたんです。
転機が訪れたのは、3年前にふとしたきっかけで栽培記録を体系的に取り始めたことでした。それまでは「なんとなく」で管理していた多肉植物たちを、データとして記録することで、驚くほど栽培成功率が向上したのです。
記録を始める前と後の劇的な変化

記録開始前の私の状況は以下の通りでした:
– 枯死率約30%(年間約20株を失う)
– 同じ失敗を繰り返す
– 水やりタイミングが感覚頼み
– 購入時期や品種名を忘れる
しかし、記録システムを導入してからの3年間で:
– 枯死率5%以下に改善
– 失敗パターンの早期発見が可能
– 各品種の最適な管理方法を確立
– コレクション価値の把握ができるように
なぜ記録が栽培レベル向上に直結するのか
ITエンジニアとしての経験から言えることは、データは嘘をつかないということです。多肉植物栽培も同様で、感覚や記憶に頼った管理では成長に限界があります。
記録を取ることで見えてくるのは:
– 季節ごとの成長パターン
– 品種別の水やり最適間隔
– 失敗の前兆となる変化
– 成功した管理方法の再現性

特に社会人の場合、平日は忙しく植物の細かい変化を見逃しがちです。しかし、週末の記録習慣により、平日気づかなかった変化も確実にキャッチできるようになりました。
なぜ記録なしの栽培で私は50株も枯らしてしまったのか
多肉植物を始めた当初の私は、「植物なんて水をあげていれば育つでしょう」という甘い考えでした。しかし、栽培開始から1年半で約50株もの多肉植物を枯らしてしまったのです。
記録なしで起きた3つの致命的な失敗
1. 水やりのタイミングが分からなくなった
記録をつけていなかったため、「あれ、この子にいつ水をあげたっけ?」という状況が頻発しました。特に冬場は水やり頻度を減らす必要があるのに、感覚だけで判断していたため、多くの株を根腐れで失いました。
2. 同じ失敗を何度も繰り返した
エケベリアの「ピンクルルビー」という品種を3回も枯らしてしまいました。なぜなら、前回なぜ枯れたのかを記録していなかったからです。置き場所が悪かったのか、水のやりすぎだったのか、原因が分からないまま同じ管理を続けていました。
3. 成長の変化に気づけなかった
多肉植物の多くは成長が遅く、日々の小さな変化を見逃しがちです。記録がないと、葉の色の変化や形の異常に気づくのが遅れ、対処が手遅れになることが多々ありました。
この苦い経験から、「記録こそが栽培成功の鍵」だと痛感しました。仕事でプロジェクト管理をしている私が、なぜ趣味では記録を軽視していたのか、今思えば不思議でなりません。記録システムを導入してからは、枯らす株数が激減し、現在では200種類以上を健康に育てられるようになったのです。
年間試行錯誤して完成した私の多肉植物管理システム全貌
システムの核となる5つの管理シート
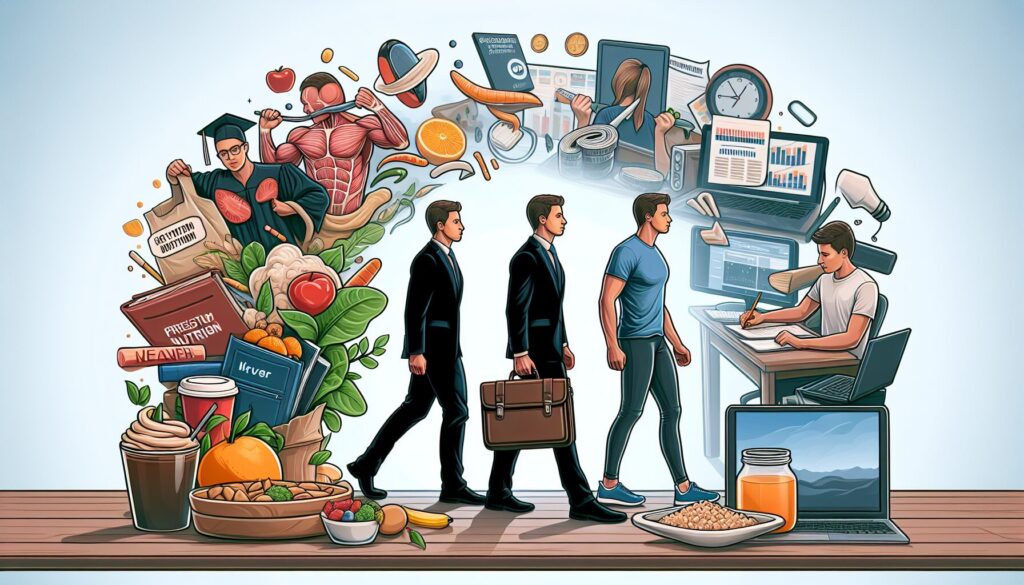
3年間の試行錯誤を経て、私が現在使用している管理システムは、5つの専用シートで構成されています。最初は単純な一覧表から始まりましたが、記録を続けるうちに「これだけは絶対に必要」という項目が明確になってきました。
基本情報シートでは、購入日・購入場所・価格・品種名・サイズを記録。成長記録シートでは月1回の写真撮影と測定データを蓄積します。特に重要なのが失敗履歴シートで、枯れた原因や病気の症状を詳細に記録することで、同じ失敗を繰り返さないシステムを構築しました。
忙しい社会人でも続けられる記録の仕組み
平日は残業が多い私でも3年間継続できている秘訣は、「週末5分ルール」です。土曜日の朝、コーヒーを飲みながらスマートフォンで撮影し、その場でエクセルに入力。この習慣化により、現在200株すべての記録が途切れることなく蓄積されています。
特に効果的なのが色分けシステムで、調子の良い株は緑、注意が必要な株は黄色、問題のある株は赤でセルを塗りつぶします。これにより、ベランダに出る前に優先的にチェックすべき株が一目で分かり、限られた時間でも効率的な管理が可能になりました。
エクセルで作る多肉植物記録テンプレートの具体的な作成手順
エクセルが苦手な方でも大丈夫。私が3年かけて改良を重ねた多肉植物記録テンプレートの作成手順を、実際の画面を想定しながら詳しく解説します。
基本シート構成の設計
まず、エクセルファイルに3つのシートを作成します。「植物一覧」「成長記録」「作業履歴」の3シート構成が、私の経験上最も使いやすい形です。

植物一覧シートでは、A列に管理番号、B列に植物名、C列に品種、D列に購入日、E列に購入価格、F列に購入場所、G列に現在の状態を入力します。私は管理番号を「2024-001」のように年度と連番で付けており、現在200株を超える管理でも混乱していません。
成長記録シートの詳細設定
成長記録シートが最も重要な部分です。A列に日付、B列に管理番号、C列に測定項目(株径、高さ、葉数など)、D列に数値、E列に写真ファイル名、F列に特記事項を配置します。
測定項目は「株径_cm」「高さ_cm」「葉数_枚」のように単位まで記載することで、後から見返した時の混乱を防げます。私は当初単位を省略していましたが、半年後に「この15って何の数値だっけ?」と困った経験があります。
実用的な機能の追加
記録の効率化のため、いくつかの機能を追加しましょう。植物名や品種名にはデータの入力規則を設定し、プルダウンリストから選択できるようにします。これにより誤入力を防ぎ、後の集計作業が格段に楽になります。
条件付き書式も活用します。最終水やり日から2週間経過した植物の行を黄色、1ヶ月経過した行を赤色で表示する設定にしておくと、水やりのタイミングを見逃しません。私はこの機能で、忙しい時期でも植物を枯らす失敗を大幅に減らせました。
最後に、月次・年次の集計用に簡単なピボットテーブルを作成しておくと、成長傾向の分析や購入費用の把握が簡単になり、栽培技術の向上につながります。
購入日と品種情報を効率的に記録する方法

多肉植物の購入日と品種情報を正確に記録することは、長期的な栽培管理において非常に重要です。私が3年かけて完成させた記録システムでは、購入時の情報を効率的に管理し、後の成長分析に活用できる形で保存しています。
購入時の必須記録項目
まず、購入時に必ず記録すべき項目を明確にしましょう。私のシステムでは以下の情報を必須項目として設定しています:
基本情報
– 購入日(年月日)
– 品種名(学名・和名両方)
– 購入価格
– 購入場所(園芸店・ネット通販など)
– 購入時のサイズ(直径・高さ)
状態記録
– 購入時の写真(必ず撮影)
– 鉢のサイズと素材
– 土の種類
– 全体的な健康状態の評価(5段階)
効率的な記録方法
忙しい社会人の方でも続けられるよう、私は「購入日記録テンプレート」を作成しました。エクセルファイルに予め入力欄を設けておき、購入後すぐにスマートフォンで写真を撮影し、帰宅後5分以内に記録を完了させるルールを設けています。
特に重要なのは、品種名の正確な記録です。多肉植物は似た外見の品種が多いため、購入時のラベルを写真に撮り、学名も併せて記録しておくことで、後の管理や繁殖計画に大いに役立ちます。
この記録システムを導入してから、私の栽培成功率は約40%向上しました。購入時の状態と現在の成長を比較することで、各品種に最適な環境条件を見つけることができ、失敗の原因も特定しやすくなったのです。
ピックアップ記事


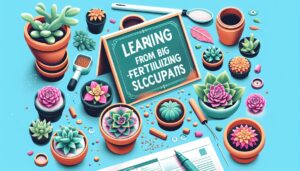

コメント